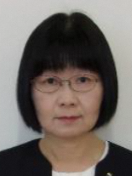学問理論と現場の実践
研究者教員と実務家教員がハイブリッドな教育研究をサポートします
農業経営学科では、稲作、果樹、野菜・花き及び畜産の各専攻分野に研究能力のある教員と実務能力のある教員を配置するほか、養成する人材像に関連の高い農産加工及び経済・経営の専任教員も配置し、理論と実践とを関連付けて学べるハイブリッドな教育研究ができる体制を確保しています。
農業経営学科の
専任教員 |
学科長 |
研究者教員 |
実務家教員 |
教員数計 |
| 1名 |
7名 |
11名 |
19名 |
印刷用のPDFファイルのダウンロードはこちら
経営経済担当
 小沢 亙
小沢 亙
 |
<例えば、こんな研究をしています>
- 地域の資源探索と問題解決手法の研究
- 農業人材のスキルアップに関する研究
- 農業関連経営体の効率性に関する研究
|
<学生・受験生へのメッセージ>
農林業経営者は自身が持っている資源、獲得できる資源を最大限に活かしながら、経済環境の変化や制度・政策の変化に対応して、経営体を継続します。そのために必要な経済や経営に関する知識と考え方を獲得しましょう。
|
<模擬講義>
- テーマ『農産物に対する価値観の違い-農業者と消費者-』
生産を行う農業者の農産物に対する価値観とそれを食料品として消費する消費者の価値観との違いを価値(金額)で考えて、農と食の関係性を考えてみます。
|
 黒瀧 秀久
黒瀧 秀久
 |
<例えば、こんな研究をしています>
- 地域活性化と農業6次産業化に関する研究
- 地域循環型農業の研究
- 食料自給率と食料安保論に関する研究
- 地域農林業の流域管理システム
|
<学生・受験生へのメッセージ>
農業は、人間の生活において一番基礎となる衣食住のうち、食料を供給する産業である。人類は今から一万年前にさかのぼって農業を開始し今日に至っている。その歴史を踏まえて、今後の日本の農業のあり方を展望しましょう。
|
<模擬講義>
- テーマ『世界の食料需給と農業のあり方について』
世界の農業は、ウクライナ問題やグローバルサウス問題の中で、食料生産が緊迫した状態にあります。こうした影響を受けて、我が国の農業がいかなる展望をしたらいいのかをみなさんとともに考え、食と農の意義を追求します。
|
 胡 柏
胡 柏
 |
<例えば、こんな研究をしています>
環境に配慮した先端的な農業経営や元気な地域社会を創るためにどうすればよいかについての研究を行っています。例えば、こんな研究をしています。
- 農業経営の実態把握と経営評価手法の開発
- 環境保全/有機農業の技術と経営の実態把握、拡大に向けた革新的取組の効果解明
- 有機農産物の消費形成と市場拡大の条件解明
など |
<学生・受験生へのメッセージ>
農業は経済的に成り立ち、社会的・環境的に持続可能な産業でなければなりません。新しい時代にふさわしい元気な農業経営を目指す皆さんと志を共有し、ともに学び、耕していくことを楽しみにしています。
|
<模擬講義>
- テーマ『農と食の世界へようこそ~農の未来は明るい~』
この20年間における農学の進展、近年大きく注目されている農業経営研究のトピックス、先端的な農業経営が求める人材像などを中心に、大学が新しい時代の農学に興味を持つ皆さんにどのような成長の舞台を提供できるかについて考えてみます。
|
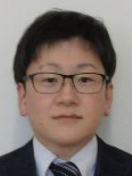 吉仲 怜 吉仲 怜 |
<例えば、こんな研究をしています>
- 果樹作経営の省力栽培に関わる経営評価
- 水田作経営の経営戦略
- 地域農業の担い手と農業労働力問題
- 農村RMO等、農村地域づくりの支援
|
<学生・受験生へのメッセージ>
全国各地で様々な農業が行われています。現場で活躍する農林業経営者に学びましょう。
|
<模擬講義>
- テーマ①『農業経営に関わるお金の話』
作物生産のコスト(費用)が増加している、同じものでも売り方によって販売価格が異なる、など、農業経営を行っていくうえで重要なお金に関わる話題を提供します。
- テーマ②『農業経営を取り巻く地域農業の姿』
農業経営を行う上で、地域の有り様を知ることは重要です。地域農業の姿がどのようになっているのか、統計資料などから見ていきます。
|
稲作・病理担当
 齊藤 邦行 齊藤 邦行 |
<例えば、こんな研究をしています>
- 水稲・ダイズ品種の多収性の解析
- 地球温暖化が作物生産に及ぼす影響
- 水稲有機栽培に関する生産生態学的研究
- 作物の物質生産に及ぼす暗呼吸の影響
- 水稲の窒素利用効率の向上
- ダイズの耐倒伏性向上に関する研究
|
<学生・受験生へのメッセージ>
稲のことは稲に聞け、農業のことは農民に聞け(横井時敬)をモットーに、環境保全と地力維持を前提とした圃場作物の多収穫・高品質・安定・低コスト・安全安心・持続性に調和のとれた作物生産技術開発を目標としています。AIやロボット、IoTといった先端技術を活用したスマート農業技術、温暖化など気候変動に適応した品種や栽培技術、温暖化ガス削減栽培技術、持続可能な有機農業技術の開発や普及が喫緊の課題です。
|
<模擬講義>
- テーマ①『地球温暖化が作物の生産性と品質に及ぼす影響』
気候温暖化がイネ、ダイズ、コムギの生育、収量、子実品質に及ぼす影響を温度勾配チェンバーを用いて解析した結果を紹介する。
- テーマ②『ダイズ複葉の運動と環境条件との関係』
ダイズの葉は光に反応して、位置を様々に変化させる向日運動が認められている。その運動の測定方法の確立と光合成に及ぼす影響を解析した結果を紹介する。
- テーマ③『水稲の有機栽培に関する生態学的研究』
岡山大学で10年間有機栽培を継続し、収量性と雑草・病害虫の発生の経年変化を調査し、ヒエ抜き(除草)を2回程度行うことにより、慣行栽培に匹敵する収量を確保できることを実証した研究を紹介する。
- テーマ④『美味しいお米を科学する』
お米の食味に及ぼす要因を品種、産地、気象条件、栽培法、炊飯方法などから解説する。米飯の食味と化学成分、外観、粘り、硬さ、物理的特性との関係を解析した結果を紹介する。
|
 宮坂 篤 宮坂 篤 |
<例えば、こんな研究をしています>
- 水稲の病害に関する研究
- 麦類の病害に関する研究
- 新しく発生した病害に関する研究
|
<学生・受験生へのメッセージ>
植物保護科学は、作物をいかにして病気、害虫、雑草から守るかという学問です。農業生産向上と生物多様性を目指します。新しい大学で是非一緒に学びましょう。
|
<模擬講義>
- テーマ『圃場に新しい病気が発生したらどうする?』
自分の水田・畑に今までに見たことのない病気が発生しました。さて、あなたならどうしますか? どのように対応していけばよいか一緒に考えてみましょう。
|
 柴田 康志 柴田 康志 |
<例えば、こんな研究をしています>
水稲、大豆の 省力栽培、低コスト栽培、高品質栽培、多収栽培など、いろいろな栽培技術の研究
|
<学生・受験生へのメッセージ>
どうしたら水稲や大豆で、
楽をして、たくさんのお金を稼げるか・・・
いっしょに考えてみませんか!!
|
<模擬講義>
- テーマ『美味しいお米のつくり方』
水稲の品種育成、栽培技術などの紹介
|
 塩野 宏之 塩野 宏之 |
<例えば、こんな研究をしています>
- 土壌中の養分量を考慮した適正施肥に関する研究
- 地域の未利用有機性資源を土づくりに利用する研究
- 水田から発生する温室効果ガス(メタン)を削減する研究
|
<学生・受験生へのメッセージ>
土壌・肥料学は、土壌微生物等を対象としたミクロな視点から、地球環境まで扱う幅広い学問です。この魅力ある分野について、是非学んでみませんか。
|
<模擬講義>
- テーマ『水田から発生する温室効果ガスの削減技術について』
水田からは、温室効果ガスの1つである「メタン」が発生します。その発生メカニズムを考慮した上で、生産現場で適用できるメタン発生量の削減技術をご紹介します。
|
果樹担当
 阿部 和幸 阿部 和幸 |
<例えば、こんな研究をしています>
- ニホンナシ、クリ、リンゴ、オウトウなど果樹の品種開発
- ニホンナシ、リンゴへの病害抵抗性の付与に関する研究
- 自家和合性など有用形質を備えた果樹の育種素材の作出と遺伝解析
|
<学生・受験生へのメッセージ>
食味が良く外観の美しい果物は暮らしを豊かにしてくれます。そのような魅力ある果実を生産する上で、果たしてどのような栽培技術が駆使され、また特長ある品種が利用されているのでしょうか?本学で果樹園芸学と高品質果実生産技術の基礎から応用まで学んでみませんか。
|
<模擬講義>
- テーマ『果物の科学』
バラエティーに富み美味しい果物。花が咲いて受粉・受精を経て結実し、小さな実が生長して甘くジューシーな果実になるまでの、果樹の生理特性について解説します。また、果物の品種改良について、その狙いや実践例を紹介します。
|
 石黒 亮 石黒 亮 |
<例えば、こんな研究をしています>
- 寒冷地果樹(オウトウ、セイヨウナシ、リンゴ等)を中心とした品種開発、各主要形質の遺伝様式、成熟生理、樹体生育等に関する研究
- 寒冷地におけるカンキツの生育、果実特性に関する研究
- 加工専用果樹の省力的栽培体系について(研究予定)
|
<学生・受験生へのメッセージ>
果樹栽培において、共通の基本技術以外は、正解はありません。いろいろなアプローチから導き出されるやり方があるはずです。それは果樹園にたくさんあるはずです。皆さんと一緒に果樹園で答え探しをしましょう。また、先進農家の方々との対話や行政施策の中から栽培技術、販売戦略などの課題解決方法を学びましょう。
|
<模擬講義>
- テーマ『果樹新品種の誕生秘話(「生みの親」と「育ての親」)
農作物の品種改良の始まった当時の共通して掲げられたであろう目標は「これまでにない、おいしい「夢」の品種」だったと思われます。育種家(生みの親)はそんなロマンを追い求めて育種に取り組んできました。その一方で、誕生した品種の一握りしか広く普及していない。それは、新品種にも欠点があり、その欠点を克服するために、たゆめぬ努力をした「人」(育ての親)がいたからこそ普及に至りました。そんな「人」たちが「夢」を追いかけて広く普及させた物語について、皆さんもおなじみの果樹品種について、お話しします。
|
 多田 史人 多田 史人 |
<例えば、こんな研究をしています>
- 果樹の品種開発を効率化する栽培技術、遺伝子技術(DNAマーカー選抜、GWAS解析、ゲノミックセレクション)の研究
- 果樹におけるスマート農業の研究
|
<学生・受験生へのメッセージ>
果樹栽培の基本から近年開発された品種、栽培技術、遺伝子技術等について、本学の実習や講義で論理的に学び、農業の実践力を身につけていきましょう。
|
<模擬講義>
- テーマ『遺伝子技術を利用した効率的な果樹の新品種開発について』
果樹の新品種開発には広大な圃場と長い年月が必要となりますが、近年、遺伝子解析技術が進歩したことで、DNAマーカーを用いた有用形質を持つ個体の効率的な選抜が可能となっています。講義では、遺伝子解析技術を用いた有用形質のDNAマーカー探索や利用の実際について紹介します。
|
野菜・花き担当
 佐藤 武義 佐藤 武義 |
<例えば、こんな研究をしています>
これまで、主要な花き類の生理生態的特性の解析と新しい生産技術の開発及び新規の品種や品目の栽培技術の研究開発及び普及に取り組んできました。具体的には、以下のとおりです。
- LED光源等の光波長を活用したトルコギキョウの切り花の高品質・計画生産技術の開発と普及。
- 光合成特性や光形態形成反応及び日長反応特性の解析をベースにした技術開発
- サクラ「啓翁桜」の効率的な休眠打破技術の開発と普及。
- 低温処理、温湯処理、ジベレリン等の植物生育調整剤の組み合わせなどの解析をベースにした技術開発
- 新規の切り花や切り枝の生産技術の開発と普及。
- 花芽分化特性、休眠特性、温度・日長感応性等の解析をベースにした技術開発
|
<学生・受験生へのメッセージ>
園芸、農業は活き物であり、日々発展しています。バイオサイエンスの最新の知見等を活かし、園芸、農業の発展方向を見据えて将来像を描きながら、学修・研究に取り組んでまいりましょう。併せて、新しい大学における新たな交流、五感の育み、知識の蓄積、地域文化の享受等、いろいろな期待が膨らみます。
|
<模擬講義>
- テーマ『LED光源等の光波長特性の花き類の生育・開花反応への活用について』
LED光源等の利用が、長日性花き類、短日性花き類の生育、花芽形成、開花、商品性等に及ぼす影響に関連して、光周性や光形態反応等の知識を踏まえて最新の知見を紹介します。
|
 古野 伸典 古野 伸典 |
<例えば、こんな研究をしています>
- 積雪寒冷地域における園芸用温室の熱収支解析
- 栽培中に燃油をまったく使わないパプリカ栽培
- 光センサーを利用したえだまめの品質評価と栽培改善
|
<学生・受験生へのメッセージ>
スマート農業とは、異分野技術の融合です。新しい発想で、新しい技術を生み出し、ワクワクするような農林業を創りましょう。
|
<模擬講義>
- テーマ『雪国でのハウス栽培の工夫と最新技術』
山形県など東北各県は雪国と言われますが、各地でハウス栽培が行われ、野菜類や花き類が生産・出荷されています。こうした農産物のおかげで私たちの生活が豊かになっていますが、近年の原油価格高騰もあり、生産工程では様々な工夫がされています。また、二酸化炭素の排出抑制などにつながる新しい技術も開発されています。本講義では、基本的な理論と、生産現場の実践例を紹介します。
|
 森 和也 森 和也 |
<例えば、こんな研究をしています>
- 野菜類の省力、高品質、安定生産に関する研究
- 温暖化や気象変動に対応するための研究
- 農薬だけに頼らない、病害の抑制、軽減に関する研究
|
<学生・受験生へのメッセージ>
栽培・生産理論や技術は、農業経営を発展させるための重要な要素で、必要な知識や技術は実に幅広く、奥深いものです。基本をしっかり習得し、応用できる人材となれるよう、共に学びましょう!
|
<模擬講義>
- テーマ『山形の自然環境を生かした野菜栽培の知恵と理論』
山形県には多様な気候風土の地域があり、それぞれで特徴的な野菜栽培が行われています。それらは昔ながらの知恵であるとともに、地域の気象条件を巧みに生かした、理論的かつ合理的な栽培方法でもあります。いくつかの例を基に、それらについて考えてみます。
|
畜産担当
 齊藤 政宏 齊藤 政宏 |
<例えば、こんな研究をしています>
これまで、
- 肉用牛、乳用牛、豚等の家畜の診療
- 牛の受精卵移植、人工授精に係る調査研究
- 農場防疫の強化
- 家畜伝染性疾病の清浄化対策
- これらに係る海外技術協力
等に取り組んできました。
本学では、特に農場防疫の強化を研究してまいります。 |
<学生・受験生へのメッセージ>
最近のわが国内外では、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ、口蹄疫、アフリカ豚熱などの重大な家畜伝染病が猛威を振るっています。これらの侵入を防ぐため、畜産農家をはじめとする畜産関係者は皆、家畜伝染病対策に厳しく取り組んでいます。また、消費者をはじめとする多くの国民からは、畜産物の安全・安心を求める声が高まっています。そのような中、家畜衛生学では、畜産農家にとって必須の家畜伝染病の侵入防止対策、生産性及び安全性の向上のための衛生管理、さらにアニマルウェルフェア・SDGsへの配慮の取組等を扱ってまいります。畜産を志す学生は もちろん、畜産農家と連携する耕種農業を志す学生におかれても、是非学んでみませんか。
|
<模擬講義>
- テーマ①『日本の獣医さんが開発途上国で活動しました』
パナマでの乾季の生産性向上の取組事例を中心に、日本の畜産技術をもとに開発途上国で課題解決に取り組んだ事例を紹介します。
- テーマ②『家畜の健康を守る、畜産物の安全・安心を守る』
農場での日々の家畜の健康管理・防疫管理から、農場HACCP、GAPといった消費者から求められる畜産物の安全・安心のための取組について、説明します。
|
 庄司 則章 庄司 則章 |
<例えば、こんな研究をしています>
- 牛肉のおいしさ成分に関する研究
- 肉牛の飼養管理に関する研究
|
<学生・受験生へのメッセージ>
飼料価格の高騰や牛由来の温室効果ガスの削減など、畜産を取り巻く環境はとても厳しいですが、解決策は必ずあるはずです。新たな発想で解決策を見つけ出し、これからもおいしい畜産物を消費者に届けていきましょう。
|
<模擬講義>
- テーマ『山形牛や米沢牛はなぜおいしい?』
山形牛や米沢牛と他県産銘柄牛との違いや、そのことがどのようにおいしさに関わるのかを紹介します。また、山形牛や米沢牛のおいしさを全国の消費者に知ってもらうために、これからどのように情報提供していくことが望ましいか、一緒に考えます。
|
 高尾 槙一 高尾 槙一 |
<例えば、こんな研究をしています>
- 家畜の飼料に関する研究
- 家畜の飼養管理に関する研究
|
<学生・受験生へのメッセージ>
山形県は食材の宝庫と言われています。皆さんもおいしい農畜産物を生産・販売できるプロフェッショナルとして活躍できるよう、実践的な学びや研究を通じてサポートしていきます。
|
<模擬講義>
- テーマ『家畜排せつ物の有効活用について』
本学で実施している授業科目「耕畜連携」の一部を模擬講義します。家畜排せつ物の適正な処理や活用方法について触れてみましょう。
|
食品加工・6次産業化担当
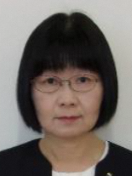
是川 邦子
 |
<例えば、こんな研究をしています>
- 農業を起点とした多様な展開(6次産業化)に関する研究
- 農産物直売に関する研究
- 女性農業者の組織活動に関する研究
|
<学生・受験生へのメッセージ>
食品加工をはじめ、農業生産を起点とした多様な展開(6次産業化)は、新たな農業経営を切り拓くチャレンジです。そして、さまざまな知識を活用できる人材が何よりも大切です。この大学で学び、自分の力を思い切り発揮できる道を探しませんか。
|
<模擬講義>
- テーマ『農業を起点とした多様な展開を考える ―食、農村そして人―』
農業を起点とした多様な展開(6次産業化)は、身近なところで数多く実践されています。それらの事例を通して、農業が持つ可能性と地域活性化への展開などを考えます。
|

鬼島 直子
 |
<例えば、こんな研究をしています>
- 米資源の高付加価値活用技術に関する研究
- 地域特産物を開発した新しい食品の開発
- 食品の食感を示す物性の評価方法の開発
|
<学生・受験生へのメッセージ>
食品の科学は、どんな人にも身近な学問で、日常の食の疑問を解決し自分の生活や健康に役立てることができます。地域の産業となるような新しい食品の開発には欠かせません。新しい知識を学び、一緒に研究しましょう。
|
<模擬講義>
- テーマ①『地域の果物から作られる魅力的な食品について』
山形県産の果物などの農産物を原料とした加工食品について、加工製造技術について解説しながら、魅力的な食品づくりについて考えます。
- テーマ②『大豆からできる様々な食品-日本食には欠かせない大豆-』
豆腐・納豆・味噌・醤油など、日本人の食卓に欠かせない様々な食品から、ちょっと意外な食品まで、大豆から作られる食品について、製造方法と合わせて解説します。
|
印刷用PDFファイル













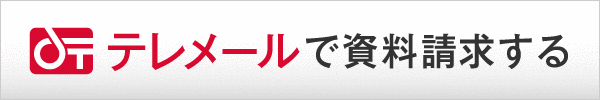



 小沢 亙
小沢 亙

 黒瀧 秀久
黒瀧 秀久
 胡 柏
胡 柏
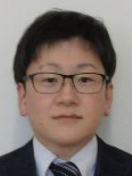 吉仲 怜
吉仲 怜 齊藤 邦行
齊藤 邦行 宮坂 篤
宮坂 篤 柴田 康志
柴田 康志 塩野 宏之
塩野 宏之 阿部 和幸
阿部 和幸 石黒 亮
石黒 亮 多田 史人
多田 史人 佐藤 武義
佐藤 武義 古野 伸典
古野 伸典 森 和也
森 和也 齊藤 政宏
齊藤 政宏 庄司 則章
庄司 則章 高尾 槙一
高尾 槙一